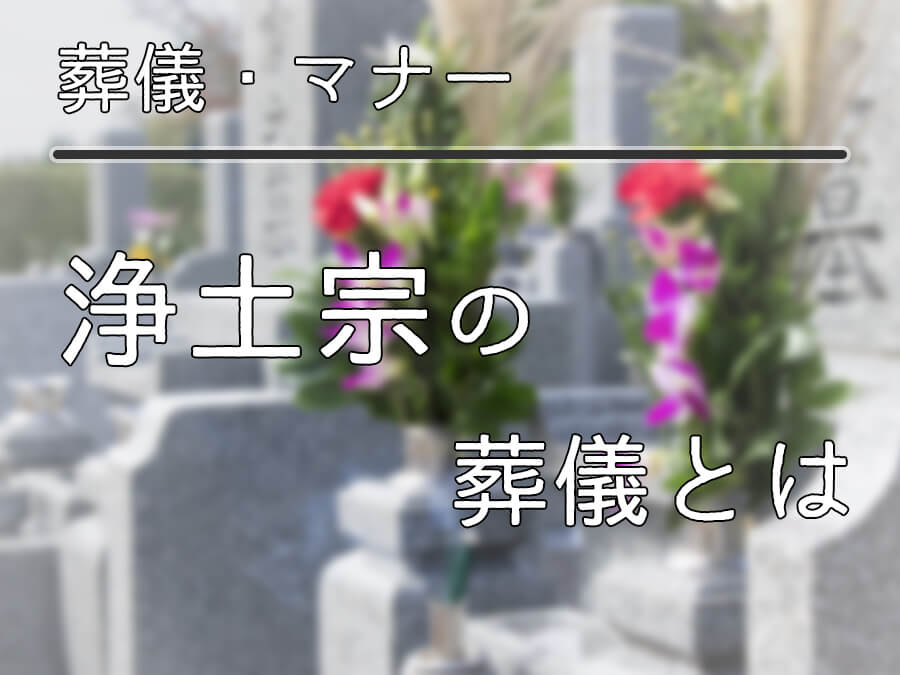浄土宗の葬儀について理解しよう
浄土宗は仏教の中でも、特に信仰する人が多い宗派のひとつです。
ただ、どのような宗派なのかきちんと理解している人はあまりいません。
浄土宗の葬儀を執り行う際には、まずは浄土宗がどのような宗派なのかをしっかりと理解しておく必要があります。
浄土宗の宗祖は法然上人という人物で、源空とも呼ばれる方です。
承安5年、つまり1175年に改宗され、本尊は阿弥陀仏阿弥陀如来です。
浄土宗の教えは、阿弥陀仏が全ての人を平等と考えていることを元にしています。
浄土宗では「南無阿弥陀仏」というお経を唱えますが、これを繰り返し唱えることで自分の人格を高めることができ、世の中のために尽くそうという気持ちが生まれるようになります。
また、この念仏を唱えることで明るく平穏な日々を過ごせるようになり、命が絶えるときにも浄土に向かうことができるという意味があります。
浄土宗の総本山は京都の東山区にあり、知恩院というところです。
さらに全国各地に「七大本山」というところがあり、ここでも古くから浄土宗の教えが守られています。
七大本山は東京都港区、京都市上京区、京都市左京区に2つ、福岡県久留米市、神奈川県鎌倉市、長野県長野市にあります。
近くにあれば、足を運んでみるのも良いでしょう。
浄土宗の葬儀について、より深く理解することができます。
浄土宗の葬儀を行う際の流れと注意点
浄土宗の葬儀を行う際には、全体的な流れを把握しておく必要があります。
浄土宗の葬儀では、まずは通夜を行います。
ここで気をつけたいこととして、「故人を寝かせる向き」があります。
故人の頭を北に向ける「北枕」で寝かせるのが基本のため、しっかりと守る必要があります。
また、ろうそくと線香は、通夜を行っている間はずっとついているようにする必要があります。
これらの火が消えてしまうとマナー違反にあたるため、必ず気をつけないといけません。
通夜の次には、葬儀を行います。
葬儀の際には序文と呼ばれるものが行われます。
これは葬儀を行う場所に仏様をお迎えする儀式です。
序文によって故人がきちんとあの世へと向かえるようになるため、とても大切な段階です。
次に正宗分というものが行われます。
これは葬儀の中心的なところにあたり、引導が行われます。
そして最後に流通分というものが行われます。
これは仏様と故人をあの世へとお送りする儀式を指します。
浄土宗の葬儀の流れは、以上のようになっています。
通夜を行った後に葬儀を行うのは他の宗派と同じですが、細かな点が異なります。
しっかり気をつけておきましょう。
浄土宗の葬儀でのマナー
浄土宗の葬儀では、焼香の仕方に気をつける必要があります。
ほかの宗派では焼香は2回の場合がありますが、浄土宗では3回です。
また、香典に記載する「表書き」の書き方は、御香典もしくは御霊前と記入するのが基本です。
これらのマナーを、しっかりと覚えておきましょう。