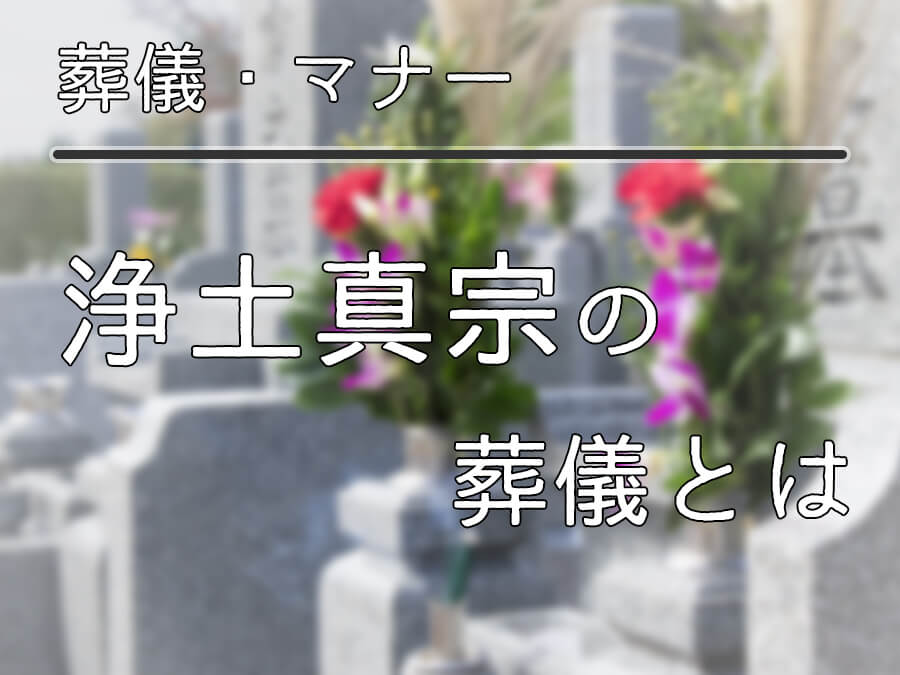浄土真宗がどのような宗派なのか説明
浄土真宗は仏教の宗派のひとつで、親鸞という人によって始められました。
浄土宗の開祖は法然という方ですが、親鸞は法然の弟子にあたる人物です。
親鸞は法然の教えを学ぶ中で独自の宗派を開きたいと考えて、浄土宗を元にして浄土真宗を始めたのです。
そのため浄土真宗は、浄土宗の考えを元にしている部分があります。
浄土真宗では「絶対他力」という考えに基づいています。
絶対他力とは「阿弥陀仏の力によって、誰でも幸せになることができる。苦痛から救ってもらうことができる」という教えです。
仏教の宗派によっては、厳しい座禅などが大切とすることがあります。
しかし浄土真宗は多くの人に受け入れやすく、仏教の中でも日本全国に広く知れ渡っている宗派のひとつとなっています。
ちなみに浄土真宗では、教徒や信者のことを「門徒」という言葉で表現するのが一般的です。
浄土真宗の葬儀を行うときは、決められた流れやマナーを守る必要があります。
浄土真宗の葬儀の流れ
浄土真宗の葬儀を行うときには、本願寺派と大谷派で異なります。
本願寺派の場合、臨終のときにはまず、故人を寝かせます。
故人の顔には白い布をかけて、葬儀を執り行います。
葬儀を行うときには僧侶の読経から始まり、続いて焼香を行います。
そして遺族や参列した方による焼香があり、火葬に進みます。
火葬の際には故人の遺骨を拾うことになります。
最後に僧侶の方が勤行という念仏を唱えることで、本願寺派の葬儀は終了となります。
次に大谷派の場合ですが、大谷派では葬儀が第一、第二と2つに分けて行われます。
葬儀式の第一では、僧侶によって読経や焼香が行われます。
これは本願寺派と同じです。
次に葬儀式の第二ですが、これが火葬にあたります。
火葬場に移動して、火葬と故人の遺骨拾いが行われます。
このように浄土真宗は本願寺派と大谷派によって、葬儀の流れが若干異なります。
どちらにあたるのかを確認して、葬儀を執り行う必要があります。
浄土真宗の葬儀を行う際のマナー
浄土真宗の葬儀では、「香典袋の書き方」に気をつける必要があります。
宗派によっては表書きに「御霊前」と書くことがありますが、これは浄土真宗では失礼にあたります。
正しい書き方は「御仏前」という表記になるため、間違えないようにしましょう。
このように書く理由は、浄土真宗の考え方に由来しています。
浄土真宗では故人の方がが亡くなった直後から仏様となる考えがあるため、上記のように記載するのが一般的なのです。
これは本願寺派、大谷派で違いはないため、覚えておきましょう。
浄土真宗の葬儀は以上のような流れ、注意点を理解しておく必要があります。
最初は慣れないかもしれませんが、前もって勉強しておきましょう。