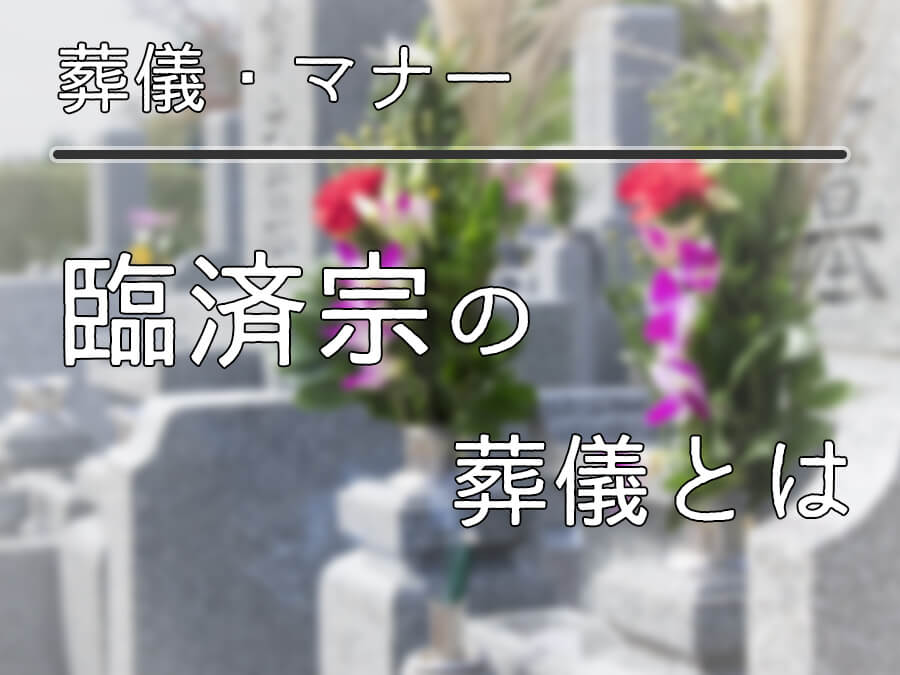臨済宗とはどのような宗派なのか
臨済宗とは仏教の宗派の一つで、鎌倉時代に始まりました。
栄西という人物によって中国から日本へ伝えられ、現在に至っています。
臨済宗では「南無釈迦牟尼仏」という念仏を繰り返し唱えます。
臨済宗は同じ頃に中国から日本に伝わった曹洞宗と似た特徴をもっており、「座禅」を大切にする教えがあります。
臨済宗では座禅をしながら弟子は師匠の出す問いに答え、その真実を見出すことが重んじられています。
鎌倉時代は特に武士が活躍していた時代ですが、坐禅の大切さは厳しい習慣を重んじる武士にとって、広く浸透しました。
また、仏教の中でも多くの人に信仰されている浄土宗や浄土真宗は、「念仏を繰り返し唱えれば、極楽浄土へ行くことができる」とされています。
これは逆にいえば「念仏を唱えさえすれば極楽へ行ける」という「他力」の考え方です。
しかし臨済宗ではこれと異なり、「苦しい行為である座禅を行うことにより、悟りの境地へ入ることができる」と考えられています。
これは浄土宗などとは逆に「自力」という考え方となっています。
浄土宗の葬儀を執り行うときは、この特徴をきちんと理解しておきましょう。
そうすれば、より適切なお葬式をすることができるはずです。
臨済宗の葬儀を行うときの流れ
臨済宗の葬儀を行うときには、全体的な流れを理解しておく必要があります。
葬儀で行われることとして、まずは導師と呼ばれる人が入場し、故人の剃髪が行われます。
剃髪では故人の髪の毛が剃られますが、現在は実際に髪の毛を剃ることはあまりありません。
カミソリを髪にあてることはしますが、ここまでで終わりとすることが多いです。
髪の毛を剃ってしまうと、葬儀の場に髪の毛が散乱してしまいます。
大切な儀式とはいえ、現代では葬儀を終えた後の髪の毛の掃除が大変です。
そのため上記のような対応で終わることが多いのです。
次に「懺悔文」というものが読まれます。
これは故人が亡くなる前の人生における後悔や罪の許しを乞うものです。
そして故人が棺に入れられたら、導師による読経が行われます。
このときには山頭念誦というものが行われます。
これは太鼓を鳴らして故人がきちんと成仏できるようにお祈りする儀式であり、臨済宗では大切なものです。
山頭念誦はほかの宗派でも行われており、臨済宗でも共通して行われています。
最後に出棺が行われます。
臨済宗の葬儀における注意点
臨済宗の葬儀では、焼香の仕方に気をつけましょう。
焼香は宗派によって特にやり方に差が出やすいところなので、きちんと行い方を知っておく必要があります。
臨済宗では焼香の回数が、1回のみです。
2回や3回ではないので、気をつけてください。
臨済宗の葬儀は、以上のような流れ、注意点を守って執り行う必要があります。
開催前には、よく理解しておきましょう。